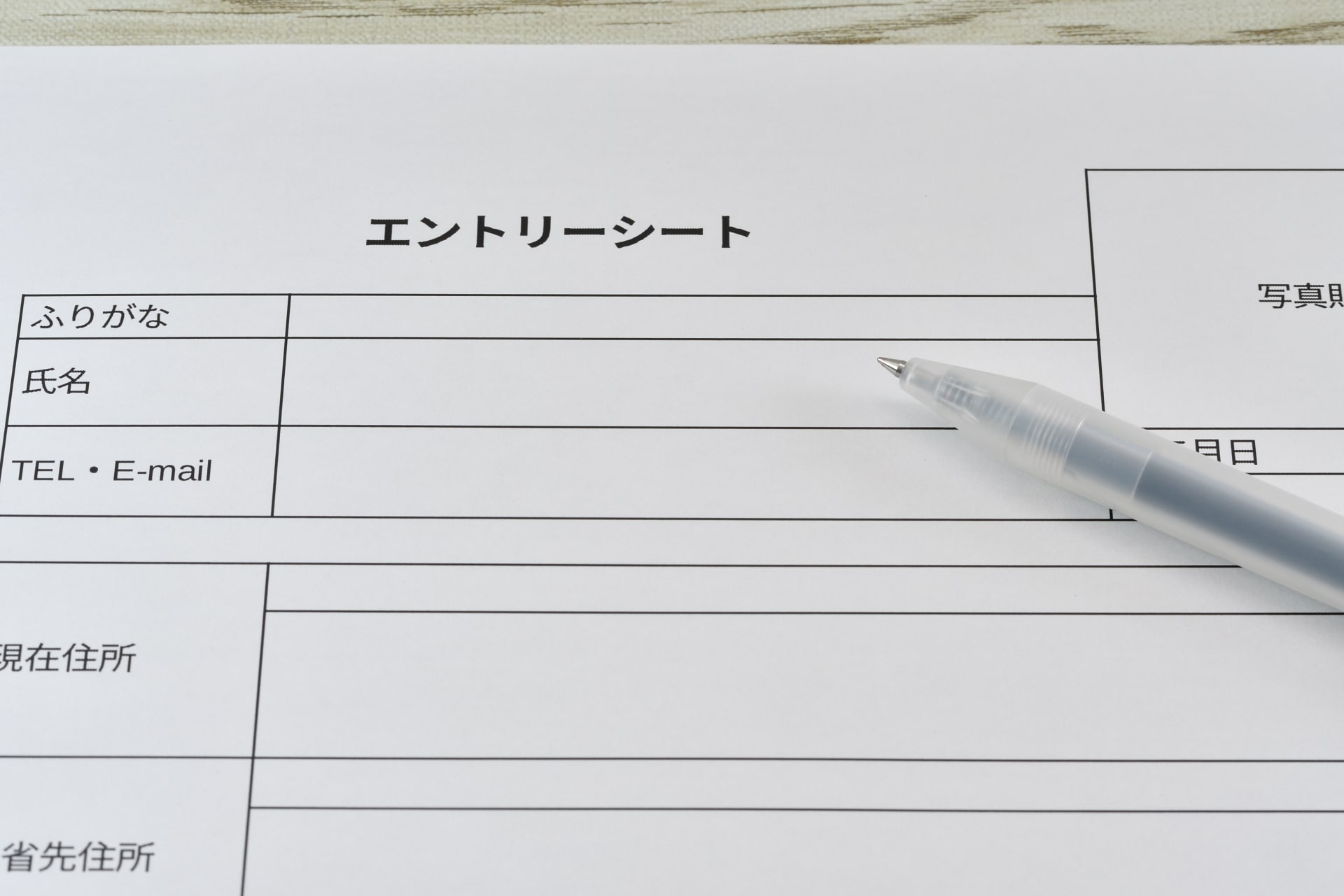新卒就活において、ES(エントリーシート)は多くの学生が避けては通れない“第一関門”です。しかし、「とりあえず書いて出す」程度の認識では、選考の通過率は上がりません。ESは単なる事務的な提出物ではなく、「あなたという人間を短時間で企業に伝えるツール」であり、書き方ひとつで評価が大きく分かれます。
さらにESは、面接内容にも直結する重要書類です。ここに書かれた内容は、そのまま面接で質問されるベースとなり、場合によっては「この時点で評価が決まっていた」と言われることもあるほどです。つまりESは、「選考を左右する分岐点」であるという認識が必要です。
企業はESで何を見ているのか?
ESを書く上でまず重要なのは、「企業が何を見ているのか」を理解することです。よくある誤解は、「面白い経験」「珍しい成果」を書かないと通らないと思ってしまうこと。しかし企業が本当に見たいのは、エピソードの珍しさよりも、そこに表れる“考え方”や“行動”の傾向です。
見られているポイント1:論理的思考と表現力
限られた文字数の中で、自分の考えを伝えるには論理性が不可欠です。読み手が「読みやすい」「理解しやすい」と感じられる構成になっているかどうかが評価の分かれ目になります。
結論から始まっているか?
内容に一貫性があるか?
主張とエピソードが対応しているか?
こうした要素は、ビジネスの現場でも求められる力です。
見られているポイント2:再現性のある行動特性
企業はESから「この人がうちに入ったら、どんな風に行動するのか?」を読み取ろうとしています。つまり、過去の行動に表れる“再現性”を重視しているのです。
例えば、「困難を乗り越えた経験」が書かれていても、行き当たりばったりだったのか、計画的に行動したのかで印象はまったく異なります。
問題にどう気づいたのか
どんな手段を選んだのか
その結果、どんな学びがあったか
このような“行動の背景”が見える構成が理想です。
見られているポイント3:企業との親和性(マッチ度)
エピソードがどれだけ立派でも、その企業が求める人材像とズレていれば評価は上がりません。企業ごとに、「行動力重視」「協調性重視」「粘り強さ重視」など、期待される人物像が異なるからです。
企業はESを通して、「この学生の強みは、当社でどう活かせるか」を見極めようとしています。したがって、自分の特性をアピールするだけでなく、相手企業の文化や価値観を意識した表現が重要になります。
なぜ似たようなESばかりになるのか?
就活生の多くが悩むのが、「自分のESがどれも似たような内容になってしまう」という点です。この原因は以下の3つに集約されます。
原因①:「自分をどう見せたいか」より「何を書けば正解か」を優先してしまう
多くの学生は、ネットや先輩のES例を参考にするあまり、「正解っぽい構成」に引っ張られ、自分の言葉を失ってしまいがちです。その結果、どれも似通った“優等生的なES”になってしまい、差別化ができなくなります。
原因②:自己理解が浅いまま書き始めてしまう
ESは“自己分析の成果物”です。自己分析が浅ければ、当然ESの内容も薄くなります。「どの経験を取り上げるか」「何を強調するか」という判断軸がないと、エピソードの選定も曖昧になりがちです。
原因③:企業の求める人物像を無視してしまう
「とにかくたくさん出そう」と思ってテンプレートを使い回すと、企業に響かないESになってしまいます。企業が欲しい人物像とズレたまま提出されたESは、「読まれた時点でスルーされる」こともあります。
良いESに共通する3つのポイント
ここまでの内容を踏まえて、「通過しやすいES」には次の3つの共通点があります。
最初の一文で結論を述べている
読み手は数多くのESを読むため、「結論から述べる」ことが読みやすさに直結します。例:「私の強みは、課題を細分化して着実に解決していく力です。」
エピソードが“結果”ではなく“プロセス”にフォーカスしている
結果だけを強調するESは評価されにくく、過程での思考・行動・工夫を伝えることが重要です。
企業に合わせて表現をチューニングしている
同じ強みをアピールするとしても、企業によって伝え方を変えることが通過率を上げるカギです。
¥¥ ES作成の基本構成を理解する
エントリーシートは企業ごとに形式が異なるものの、大まかな構成には共通項があります。基本的に、次の3〜4つの設問カテゴリが存在します。
自己PR
→ あなたの強みや特性を伝える項目。
→ 「その強みをどうやって身につけたのか」「どう発揮したか」が問われる。
学生時代に力を入れたこと(通称:ガクチカ)
→ 一定期間継続的に努力した経験の中で、思考力・課題解決力・リーダーシップなどが見られる。アルバイト、部活、ゼミ、ボランティアなどが題材になる。
志望動機・企業選びの軸
→ なぜこの企業を志望するのか、なぜこの業界なのか、なぜこの職種なのかを問う設問。企業とのマッチ度を測る目的がある。
将来やりたいこと・キャリア展望
→ 中長期的なビジョンを通して、企業との方向性の一致や継続意欲を見られる。
これらの設問をどう構成し、どう表現するかが通過率を左右するポイントです。
書きやすくなる「PREP法」の活用
ESに限らず、論理的に書くための基本フレームワークとしてよく使われるのが「PREP法」です。
PREP法とは?
P(Point)=結論
R(Reason)=理由
E(Example)=具体例
P(Point)=まとめ
たとえば自己PRで「私の強みは粘り強さです」と主張するなら、
なぜそれが自分の強みなのか
その強みが発揮された具体的な経験
そこから何を学び、どう活かせるのか
という流れで展開することで、読み手が理解しやすい文章になります。
書く順番は「設問順」ではなく「書きやすい順」でOK
就活生の多くが「ESを書くことが苦手」と感じる理由のひとつは、「設問順に書こうとして詰まってしまう」ことです。
実際には、書きやすいものから手をつけて構いません。
おすすめの順番
学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)
→ 具体的エピソードがあれば、書きやすいことが多い。
自己PR
→ ガクチカと同じ経験をベースに構成できる場合もある。
志望動機
→ ガクチカや自己PRが決まってからの方が説得力が増す。
将来のビジョン
→ 志望動機の延長線上で考えると自然。
各設問の“落とし穴”と改善策
それぞれの設問には、よくある失敗例があります。ここでは主要な3つについて見ていきます。
自己PR:抽象的すぎる
NG例:「私は人と話すのが得意です」
→ 抽象的すぎて、何が強みなのか伝わらない
改善策:「私は相手の立場に立って丁寧にコミュニケーションをとる力があります。飲食店のアルバイトで、クレーム対応を任された際…」
→ 具体的な経験+その中での自分の行動を盛り込む
ガクチカ:結果のみを強調しすぎる
NG例:「ゼミで優勝しました」「売上を200%に伸ばしました」
→ 成果だけでは伝わらない
改善策:プロセスを丁寧に描く。「その目標をどう設定し」「どんな困難に直面し」「どう工夫して」「どのように乗り越えたか」
→ 結果はプロセスの“証拠”として最後に添えるイメージ
志望動機:使いまわし感が強い
NG例:「貴社の理念に共感し、業界をリードする姿勢に惹かれました」
→ どの企業でも言える内容は評価されにくい
改善策:「貴社が手がける●●事業において、“〜〜〜”という取り組みに魅力を感じました。自身の●●経験と重なり、強く共感しました」
→ 企業独自のポイントに触れ、自分との接点を具体化する
見直しのポイント:提出前に確認すべきチェック項目
書き終えたら必ず見直しを行いましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。
内容面
結論が冒頭にあるか
一貫性のある構成になっているか
具体性があり、読み手にイメージさせられるか
企業ごとにカスタマイズされているか
表現面
誤字脱字はないか
文末表現が「です・ます」で統一されているか
一文が長すぎないか(60文字以内推奨)
主語と述語のねじれがないか
よくあるESの書き方事例と添削ポイント
ESにおいて重要なのは、自分が「どう考え」「どう動いたか」をわかりやすく相手に伝えることです。今回は、実際に多くの学生が書くような内容をベースに、どこが評価され、どこが改善されるべきかを具体的に解説していきます。
自己PR:抽象から具体への変換がカギ
ES例文(改善前)
私の強みはリーダーシップです。大学ではサークルの代表を務め、メンバーをまとめて活動を円滑に進めました。責任を持って仕事をやり遂げる姿勢は、社会でも活かせると考えています。
問題点
「リーダーシップ」というワードが抽象的。
サークル代表をやった事実だけで、どんな行動をしたかが見えない。
汎用性が高すぎて企業に響かない。
添削後の例
私の強みは、目的から逆算してチームを動かす調整力です。大学では約40名が所属するダンスサークルの代表を務め、毎年恒例の地域イベントでのステージ発表を成功させるために、演目決定から練習スケジュールまでの全体設計を行いました。演出チーム・照明チーム・出演メンバー間のスケジュール調整と進捗管理を通じて、目標に向けた段階的な実行力を培いました。
評価ポイント
「リーダーシップ」を“調整力”として具体化。
エピソードが明確で、行動と成果のつながりがわかる。
ビジネスにも通じる“段階設計”や“進捗管理”という表現が説得力を持たせている。
ガクチカ:成果より過程にフォーカス
ES例文(改善前)
私は大学時代、カフェでのアルバイトに力を入れました。接客を通じてお客様とのコミュニケーションの大切さを学びました。常連のお客様にも名前を覚えてもらえるようになり、自分の成長を感じました。
問題点
学びが「コミュニケーションの大切さ」と曖昧。
工夫や課題解決の過程が描かれていない。
誰でも書ける内容になっており、個性が見えない。
添削後の例
私は大学時代、カフェのアルバイトで「新人教育担当」として店舗の離職率改善に取り組みました。当時、3か月以内の離職が続いていたため、店舗全体で「マニュアルが機能していないのでは」と感じ、業務の中で新人がつまずきやすいポイントを洗い出しました。その上で、研修中に伝える内容をチェックリスト化し、新人が質問しやすい雰囲気づくりも意識しました。その結果、離職者はゼロになり、店長からも「教え方が他スタッフのモデルになった」と評価されました。
評価ポイント
単なるバイト経験を「離職率改善」という視点で価値づけ。
原因特定〜施策〜結果というビジネス的思考の流れがある。
他者からの評価を含め、客観的に強みが伝わる。
志望動機:企業ごとのカスタマイズがカギ
ES例文(改善前)
私は人の成長に関わる仕事がしたいと考えており、教育業界を志望しています。貴社は長年にわたって教育に関わる実績があり、研修制度も充実している点に魅力を感じています。学生時代の家庭教師経験を活かしたいです。
問題点
「教育業界ならどこでもいい」という印象。
「なぜこの会社か」が浅い。
経験と企業の接点がぼやけている。
添削後の例
私は「成長を支える仕組みづくり」に関心があり、その実現手段として教育業界を志望しています。中でも貴社は、単なる学力支援だけでなく、キャリア形成や非認知能力の育成にも注力している点に強く共感しています。私は学生時代に高校生へのキャリア講座のファシリテーションを担当し、「将来が見えない」と悩む生徒が前向きな姿勢に変わる姿を見て、自らの関わりが人の成長の一助になり得ることを実感しました。この経験を活かし、貴社のキャリア教育プログラムの開発に貢献したいと考えています。
評価ポイント
「成長を支える仕組み」という視点が軸になっている。
企業独自の取り組みと自分の経験がリンクしている。
志望動機が自己分析と業界研究を経た上で語られている。
共通のチェックポイント:書いた後に見直すべき観点
どんなにいいエピソードでも、以下のような視点で見直すことで、さらに質の高いESになります。
自分の言葉で書かれているか?
テンプレやネットの文例をそのまま使っていないか。読み手は“らしさ”を求めている。
企業との接点は明確か?
業界全体ではなく、「なぜこの会社なのか」がはっきりしているか。
一貫性があるか?
自己PRとガクチカがバラバラになっていないか。価値観や行動様式が共通していると評価されやすい。
完成度を高めるための準備がESの質を左右する
ESは書き方や表現力の前に、「何を伝えるか」を明確にする準備段階が最重要です。自己分析・業界分析・企業研究ができていなければ、どんなに整った文章でも評価されません。ここでは、ESの完成度を高めるための下準備と視点を整理します。
自己分析:強み・価値観・志向性を可視化する
自己分析は、ES全体のベースとなる作業です。特に重要なのは、「過去の経験」から「自分の強みや価値観」を一貫性をもって抽出することです。
強みの抽出方法
成功体験・失敗体験の棚卸し
自分が周囲から評価された行動・成果
困難を乗り越えた経験の分析
これらを振り返ることで、「自分がどんな時に力を発揮できるか」「どんな価値観を持って行動しているか」が見えてきます。
就活で使える自己分析ツールの活用
キャリアシートやマインドマップで構造的に整理
適性診断(リクナビ診断・キミスカなど)で客観的指標を取り入れる
面接練習で言語化の練習も兼ねる
自分の言葉で説明できる状態まで仕上げることが、ES作成に直結します。
業界・企業研究:志望動機の具体性を生む
次に大切なのは、企業への理解です。「なぜその企業を志望するのか」は、自己分析の結果と企業研究が合致していなければ説得力が出ません。
比較で見える「違い」に注目する
1社だけを深く見るのではなく、同業他社と比較することで企業の独自性や強みが浮かび上がります。
例:
教育業界:A社は個別指導重視、B社はICT教育重視
金融業界:X社は法人営業強化、Y社はリテール特化
この「違い」がESでの志望動機に説得力を与える要素になります。
OBOG訪問・インターンで得た一次情報を活用
ネット情報に頼りすぎると、どうしてもテンプレ的になりがちです。ESにおいては、「実際にOBOGに聞いた」「インターンでこう感じた」など、一次情報が高く評価されます。
設問の解釈を“勝手に決めつけない”ことが差を生む
ESには企業ごとに特徴的な質問が出されることがあります。例えば:
「あなたが大切にしている価値観は?」
「これまでの人生で最大の挑戦は?」
「当社で実現したいことを教えてください」
一見似たような質問でも、企業が何を見たいかを読み取る姿勢が重要です。
同じ「挑戦経験」でも企業によって見られる視点は違う
ベンチャー企業:主体性・スピード感
大手メーカー:継続力・チーム協働
コンサルティング:論理性・問題解決能力
同じエピソードでも、企業の文化や職種に合わせて「見せ方」を変える工夫が求められます。
ES提出後にできる「ブラッシュアップ」の考え方
一度出したESが全てではありません。面接などでも問われる可能性があるため、常に「アップデート可能な状態」にしておくことが重要です。
フィードバックをもらえる仕組みを活用する
大学キャリアセンターや就活塾のES添削
就活コミュニティでの相互添削
企業からの選考フィードバック(あれば貴重)
これらを使って、自分では気づきにくい改善点を見つけることができます。
全体のまとめ:ESは「準備」と「戦略」で差がつく
ここまでの4回にわたるES記事の内容を踏まえて、全体のまとめをします。
ESは「企業が知りたいこと」を的確に伝える文書であり、単なる自己アピールではありません。
書く前に自己分析・業界分析・企業理解を徹底することで、内容に深みと一貫性が生まれます。
PREP法などの型を活用することで、読み手にとってわかりやすい文章構成を作れます。
エピソードの具体性・説得力・個別性が、通過率を大きく左右します。
ESの良し悪しは“準備力”と“戦略性”で決まります。決して「文才」だけで差がつくものではありません。
エントリーシートは、あなたがどんな人で、どんな価値を提供できるかを企業に伝える最初の接点です。しっかりと自分自身を理解し、相手に合わせて的確に伝える力を磨いていきましょう。そうすれば、書類選考通過率は確実に向上し、面接へのチャンスも広がっていきます。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます